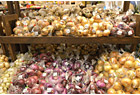農産直売所あぜみち 店舗紹介
地元の野菜を中心に、新鮮野菜をリーズナブルに提供する「農産直売所みんなのあぜみち」の店舗をご紹介します。
テンションが上がる楽しいショップにも注目!!
西川田店
-
- 所在地
- 宇都宮市西川田町287-1
- 駐車場
- 200台
- TEL
- 028-678-2398
- 営業時間
- 通常 9:00 - 19:00
- 定休日
- 1/1-1/4以外は無休
取り扱い品
上戸祭店
-
- 所在地
- 宇都宮市上戸祭町3031-3
- 駐車場
- 200台
- TEL
- 028-678-9687
- 営業時間
- 通常 10:00 - 19:00
- 定休日
- 1/1-1/4以外は無休
取り扱い品
駅東店
-
- 所在地
- 宇都宮市中今泉2-10-23
- 駐車場
- 32台
- TEL
- 028-680-5031
- 営業時間
- 通常 10:00 - 19:00
- 定休日
- 1/1-1/4以外は無休
取り扱い品
滝の原店
-
- 所在地
- 栃木県宇都宮市滝の原3-1-1
- 駐車場
- 6台
- TEL
- 028-632-5431
- 営業時間
- 通常 10:00 - 19:00
- 定休日
- 1/1-1/4以外は無休
取り扱い品
鹿沼店
-
- 所在地
- 鹿沼市千渡1754-5
- 駐車場
- 台
- TEL
- 0289-74-7030
- 営業時間
- 通常 10:00 - 19:00
- 定休日
- 1/1-1/4以外は無休